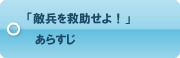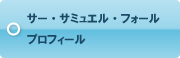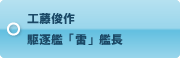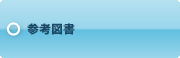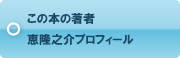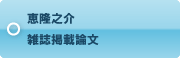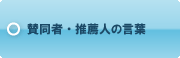見過ごせない沖縄反戦基地運動の実態 政府の抜本的政策が急務 「世界週報」1997(平成9)年 5/6-13(合併号)
恵 隆之介
めぐみ・りゅうのすけ 一九五四年生まれ。防衛大学校管理学専攻コース卒。海上自衛隊幹部候補生学校、練習艦隊を経て、護衛艦隊勤務。八二年二尉で退官。著書に『天皇の艦長・沖縄出身提督・漢那憲和の生涯』。
駐留軍用地特別措置法(特措法)の改正案が賛成多数で衆議院を通過し、懸念されていた契約拒否地主所有地の使用権原消滅に伴う法的空白状態はひとまず回避された。とはいえ、沖縄問題は今年秋に行われる日米防衛協力のための指針見直しの際にも、政党間の駆け引きに利用されるであろう。このため、沖縄の反基地運動の実態や県の実情を国民は正確に知るべきである。
ナイ・レポートに反発して代理署名拒否?
米軍用地の使用権原消滅による法的空白状態を生じせしめる発端となった、大田沖縄県知事による米軍基地強制使用に関する代理署名拒否(1995年9月28日)は、その24日前に発生した米海兵隊員による沖縄女児暴行事件が主因とされてきた。しかし、真相は別のところにある。吉元沖縄県副知事は昨年11月、その真相について重大な発言をしているのだ。
「大田知事が代理署名を拒否したのは米海兵隊員による少女暴行事件が主因ではなかった。95年2月に『ナイ・レポート』で発表された米軍アジア兵力10万人体制に対する反発であった」
この発言は、中国福建省関係者を那覇に招待して行われた「沖縄福建サミット」の席上でなされた、仮にこの発言の真意がアジアにおける米軍の存在に否定的な中国へのリップサービスであったとしても、1億2000万国民の安全保障の根幹にかかわる問題を、こう安易に利用させていいものだろうか。
一方、昨年4月、橋本首相は日米首脳会談の直前、モンデール日米大使(当時)との間で、普天間海兵隊航空基地の返還を県内移設を条件にとりつけた。この時、大田知事は、首相の努力に謝意を表明しながら、県内移設についても最大限すると語ったようである。ところが、実際は努力するどころか、沖縄の米軍兵力が削減されれば普天間基地の県内移設は必要なくなると発言し始め、昨年9月8日「米軍基地の整理・縮小と日米地位協定の見直しの賛否を問う」県民投票を実施した。知事は圧倒的多数の県民が基地縮小を指示するものと過信していたようだ。
日ごろ「基地全面撤去は県民の総意」とうそぶいていた沖縄県庁や地元マスコミは、「縮小」となればこそこれ県民の圧倒的多数が得られると思っていたに違いない。ところが、投票率自体も59.53%と予想の80%を大きく下回り、しかも基地縮小への賛成票さえ県内有権者の53%弱でしかないという結果が出てしまった。知事はこの開票結果を見て平静を装うのがやっとの状態であったという。
当然この状況は米国のマスコミにも取り上げられた。そこで、知事は今年、米国へ直接基地縮小をアピールするグループを続々派遣し始めている。3月14日、第二陣の県内学識経験者グループを前に、知事は県庁でこう発言している。
「『基地の整理・縮小を言っているのは知事だけではないか』と米国の新聞に書かれている。(そうでないことをアピールするためにも)前回は女性団を派遣した。今回は学者、そして次は私自身、次は労働団体や経済界を派遣したい。さらには大学生などを派遣することも考えている」
こうした中で、知事は4月12日、基地縮小を訴えるため米国へ出発したが、25日に行われる日米首脳会談の前に米国で一石を投じる狙いがある。
一方、昨年1月就任した橋本首相は、連立政権内部で沖縄米軍用地の強制使用と特別立法の問題が政権を分解させることを懸念し、そのカギを握る沖縄県庁への徹底した懐柔作戦に出た。その最たる材料が昨年8月に提示された沖縄振興策であり、そのための特別調整費50億円であった。とりわけ官邸は沖縄県庁との直接交渉を繰り返しつつ、大田知事の譲歩に期待した。
ところが、官邸の読みが甘すぎた。昨年9月、大田知事の代理署名正式表明から一週間後に衆議院の解散総選挙を実施したものの、自民党は単独過半数に達せず、さらに今年4月になって「特措法の改正案」が閣外協力の社民党にあっさり反対され、沖縄県知事とは物別れに終わってしまった。
ただ、沖縄県知事や社民党が一坪反戦地主3085人と連帯して反基地運動を推進したことは、今後国民の支持を失う結果になるであろう。
反基地運動の一部にチュチェ思想の影
そこでこの一坪反戦地主について言及したい。
沖縄で米軍に用地を提供している地主は、約3万2000人余人がいるものの、既に2万9000人の地主は再契約を終えている。残った3085人が契約を拒否しているが、そのうち2968人がいわゆる一坪反戦地主といわれる集団である。これらの地主の土地は合計してもわずか0.2ヘクタール。一人当たりの所有面積は30センチ四方から95センチ四方にすぎないのだ。しかも、その半数近くが本土に在住している。
実は72年の沖縄復帰の際に約3000人いた在来の反戦地主は82年には百数十人に激減しており、沖縄における米軍用地契約拒否闘争は風前の灯となっていた。そこで生まれたのがこの一坪反戦地主である。
昨年7月3日、大田知事は本土から視察にきた国会議員に「地主総数でごくわずかな一坪反戦地主に加担するのは民主主義のルールに反するのではないか」と質問された。そのとき知事は「平等原則に照らせば数の大小ではない」と反論している。
また昨年8月28日、沖縄県は「代理署名職務執行命令訴訟」の敗訴を不服として最高裁に上告したものの全面敗訴した。この結果に対し、一坪反戦地主代表世話人の新崎盛暉沖縄大学教授は「裁判は権威があるとか中立なところに判断してもらうのではなく、闘いの場として選び取っていくべきだ」と明言している(昨年8月31日付『琉球新報』夕刊)。これらの発言は、現代の法秩序に対する彼らの考え方を端的に示している。
ところで、軽視できないのが県民投票推進協議会議長など反基地運動の指導的役割を務め、一坪反戦地主でもある沖縄大学教授の佐久川政一氏の存在である。佐久川氏は「チュチェ思想研究会全国連絡会会長」という肩書きを持つ北朝鮮礼賛派の全国的主要メンバーの一人でもあるのだ。
駐留軍用地特別措置法に基づく裁決申請に関する第一回公開審理(2月21日)で、反戦地主会会長の照屋秀伝氏が発言した内容と、この一年前に佐久川氏が千葉県教育会館で開かれた「チュチェ思想と日朝友好に関する全国セミナー」で発言した「在日米軍をはじめアジア太平洋地域に駐留している米軍の銃口は朝鮮に向けられています...」(『チュチェ思想』96年3月号)という内容に類似する。さらにこの公開審理のとき、会場には韓国民主主義民族統一全国連合米軍基地対策委員長ら、韓国で反米、反基地運動を推進する活動家43人が傍聴しており、また最近の北朝鮮中央放送は「沖縄住民が反対する特措法改正は橋本首相の対米屈従を示している」と批判している。
このように、沖縄反基地運動は単なるローカルの運動では決してないのだ。
補助金を有効に活用できない沖縄
昨年8月から頻繁に行われた官邸と沖縄県庁の直接交渉の結果、沖縄県庁に比類のない政治力が集中している。「沖縄県知事は官房長官と、副知事は官房副長官と同格」と揶揄されるばかりか、従来、県政の冷却機関的存在であった県内財界でさえ、県庁に意見を同じくするようになっている。
また、最近沖縄では独立論がささやかれるようになり、従来反基地運動に中立的立場をとっていた県内識者でさえ、基地縮小、とくに海兵隊削減を発言し始めている。
反基地運動の担い手である県市町村の労組についても実態を述べる。
沖縄の市町村行政の特徴は、これら労組の意見が強いため、人件費等の固定費比率が硬直化して地域開発などの事業が困難になっていることだ。また、県内各市町村の行政面積は基地面積を減じなくても47都道府県中最下位に近く、しかもそれらが競って箱物を造り、地域エゴを強調するため広域的な地域開発が不可能になってきた。
沖縄に視察に訪れる各政党の幹部は、この結果だけを見て「沖縄にはさらなる沖縄振興策が必要」と発言しているが、従来のようなつかみ金のばらまき的施策では、沖縄はいつになっても補助金の有効活用ができないのが実態だ。しかも沖縄県知事や労組は相変わらず行政の怠慢を基地問題に転嫁し続けている。
このままでは沖縄県経済は瓦解するのではないだろうか。戦前は主要産業もなく、住民は本土への出稼ぎか海外移民へ出て行かざるを得なかった。そのため戦前の人口はピークで59万人で推移していたものが、戦後は基地ができたため、その雇用効果と高率補助の結果、人口は現在127万人台に達している。とくに72年の沖縄復帰を境にして、人口は33.4%増え、失業率も同期間比較で4.2ポイント増大して7.2%(本土3.3%=昨年9月現在)となっている。
ところが、この高率補助に甘えて県民の生産意欲は減退し、農業や漁業をはじめとして、近年あらゆる生産活動が右肩下がりになっているのだ。このため、年々約5.5%上昇する軍用地借料などの基地関連受け取りが再び沖縄経済のシェアを拡大しつつある。
県は2015年までに基地を全面撤去し、ノービザ制度などの一国二制度を柱とする国際都市構想の実現をもって経済自立化を図ると主張している。ところが、復帰25年間、復帰特別措置や沖縄振興開発法による特例で、本土企業との競争にさらされなかった地元企業は、果たしてその時、存続できるのであろうか。
それにもまして、復帰25年間に沖縄振興開発費だけでも合計4兆2943億円に上る補助を受け続けてきた県民自体が、アジアから押し寄せる労働者に職を奪われることになりはしないだろうか。