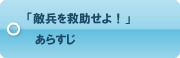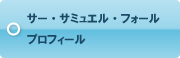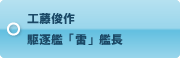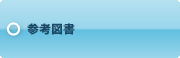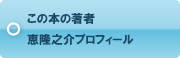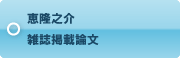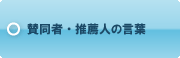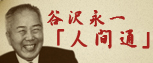沖縄を「生活保護県」にするつもりか 文芸春秋「諸君」(1997、平成9年4月号)
基地からの恩恵と国の財政補助に縋る沖縄。「甘えの構造」を絶たなければ真の自立はない。
恵隆之介 銀行員・沖縄在住大正3年、沖縄県立第一中学校(現在の首里高校)の学芸会で、生徒の一人が次のような弁論を行なっている。
「通堂から首里坂下まで見よ。そこには沖縄県人の店は一つもない。全部他府県人の店ではないか・・・」
明治という熾烈な時代を認識できなかった沖縄に他府県の商人が進出し、またたくまに沖縄の表通りは席捲された。本土に置き換えれば、東京・大阪の目抜き通りに、日本国民の経営する店が一件もないというのが、当時の沖縄の実態だった。
いま沖縄県が提唱している「国際都市構想」が実現すれば、今度は外国の企業までもが沖縄に進出し、おそらく大正時代と同じ事態を招くことになるだろう。
平成8年5月25日、返還合意が成立した普天間飛行場に隣接する宜野湾市市民会館で、米軍従業員労働組合(全駐留軍労働組合沖縄地区本部)の主催による、基地返還にともなう雇用問題を議題とするシンポジウムが開かれた。パネリストは沖縄県副知事、地元大学教授、県経営者協会会長など五氏。聴衆およそ500人の大半が軍従業員で占められた。
県内に約8300名いる軍従業員と約29000名の軍用地主(賃貸に賛成している者)は、今後予想される大幅な基地返還に対して不安を隠せないでいる。しかし、パネリストの副知事と県経営者協会会長は、国際都市構想の一端に触れてこう述べた。
「嘉手納基地跡地を国際ハブ空港に・・・」(吉元副知事)
「大那覇国際港を作り・・・」(稲嶺県経営者協会会長)
聴衆の中からは「また夢物語を」という呟きが漏れはじめ、ついにはパネリストへの批判が次々と飛び出したのである。
シンポジウムが終わりかけた頃、中年の女性が立ち上がって、こう発言した。
「どうして貴方がたは、基地撤去について安易に発言するのですか。私は軍従業員です。貴方がたには失業の心配はないでしょうが、私はこの年で解雇されたら再就職のあてもありません。貴方がたに私の生活権を左右する権利があるというのですか」
県内では論客として知られるパネリストたちも、これには誰ひとりとして反論できず、会場は一時ただならぬ空気に包まれた。
「一国二制度」の要求
すでに報じられているように、県は2015年までに沖縄の米軍基地を全面撤去させ、跡地に国際都市を建設すると明言、その中核を普天間飛行場の跡地に求めている。ただし大田昌秀県知事は、国は提示した普天間基地の県内移設にまったく協力しようとせず、「在沖米軍基地が縮小されれば県内移設をしないですむ」として、今年4月に米国政府へ兵力削減の直接交渉を行う、と発言しているのだ。
「国際都市構想」とは、そもそもどういうものなのか、平成8年8月、県が国に提出した「規制緩和等産業振興特別措置に関する要望書」によれば、主な内容は次の5項目である。
| 1 | 自由貿易地域の拡充強化による経済特別区の形成(法人税軽減、独自関税など税制上の特別措置等) |
| 2 | 那覇港のベースポート指定 |
| 3 | 魅力ある国際観光・保養基地の整備(航空運賃の大幅低減、ノービザ制度、那覇空港のハブ空港化) |
| 4 | 情報関連産業の集積 |
| 5 | 政府開発援助の活用 |
舞台裏ではしばしば県営カジノ構想も囁かれているが、いずれにせよ、これはまさに「一国二制度」の要求である。果して沖縄経済は、制度さえ変われば自立できるのであろうか。いま世界には、このような自由貿易地域が約600あるが、成功しているのは半数もない。
また仮に沖縄にノービザ制度や独自関税制度が導入されたとすれば、今度は沖縄県民が本土へ渡航する際に通関を経なければならなくなる。本土復帰前、県民があれほど望んだ本土渡航の自由を自ら撤回することになるのである。
そればかりか沖縄では、いま中国人の密入国事件が跡を絶たない。平成8年だけで94人が逮捕されたが、密入国者が県内に潜伏している可能性も捨てきれない。今年1月17日には、86人名の密入国者が沖縄本島上陸後に発見されている。沖縄近海にはそれらしき不審船が多数浮遊しており、海空からの哨戒を少しでも怠れば、大量の不法入国者が上陸する恐れがある。
沖縄の県民所得は211万円と全国でも最低レベルだが、それでも中国の40倍、ベトナムの100倍である。ノービザ制度が導入されるやいなや、諸外国の労働者が大挙して沖縄に流入してくるだろう。尖閣問題もより複雑化し、中台の狭間で極めて不安定な県政を強いられるのは火をみるより明らかだ。
なによりの矛盾は、沖縄の企業が現在、復帰特別措置や沖縄振興開発法によつ税制関係特別措置によって辛うじて存続しているという実態である。こうした法律は時限立法だが、沖縄財界が国に懇願し、すでに4回の延長を行っている。いまや、この沖縄財界が国際都市構想実現のための規制緩和を提唱し、その一方で復帰特別措置のさらなる延長を要請しているのである。
ちなみに県内企業は第三次産業に偏重しており、ほとんどが零細な小売業だ。平均自己資本率は5.6パーセントと本土平均の半分以下にすぎず、その半数近くが赤字経営である。さらに県内製造業の売上高に占める研究開発費をみても、本土平均の10分の1以下(0.3パーセント)と極端に低い数値を示しているのである。
国と県との談合
沖縄経済の実態についてはあらためて述べるとして、そもそも「国際都市構想」の成立過程は拙速にすぎたと言えよう。
平成8年6月11日、県は「国際都市OKINAWA懇話会」(以下国際都市懇話会と略す)を発足させる。県が一方的に構想を進めているという風評を払拭ため、県内の学識経験者、労働組合、マスコミ代表など25名を委員に選出し、とりわけ当時この構想に批判的だった県内財界人を役員に取り込んだ。そして、わずか3回の会合によって提言をまとめさせ、11月末の沖縄施設・区域特別行動委員会(SACO)の最終報告に間に合わせる形で国に提出した。
そころがこの間、構想推進派には願ってもない追い風が吹いていた。沖縄問題をめぐる与党内の足並みの乱れである。
周知のように、平成7年12月、当時の村山首相は「代理署名職務執行命令訴訟」を提訴し、8年3月に勝訴した。これを不服とした大田知事は7月に最高裁に上告したものの、8月28日に全面敗訴している。また国は、8年4月にいわゆる「公告・縦覧訴訟」を起こしているが、ここでも勝訴する公算が大だった。
ところが当時の連立与党内に、米軍用地強制使用と特別立法の問題をめぐって意見の対立が生じ、政権崩壊寸前の様相を呈してしまう。そのため、橋本総理(8年1月就任)は従来の沖縄施政を大幅に変更し、沖縄県庁への徹底した懐柔策に転じたのである。
平成8年8月20日、梶山官房長官の諮問的機関として「沖縄米軍基地所在市町村に関する懇談会」(以下沖縄基地懇談会と略す)を設立し、11人の委員の中に、沖縄の労組代表、マスコミ代表、財界代表など5人を取り込んだ。8月24日には加藤幹事長を連立与党の代表として沖縄県庁に派遣して、「従来の政府与党の沖縄対策は不十分であった」と謝罪させた。加藤幹事長は、防衛庁や外務省をスケープゴートにするような発言をしつつ、基地縮小と国際都市構想の実現に向けて最大限の努力をすると明言している。一方、沖縄ではその2日前の8月22日、前述した国際都市講話会が2回目の会合を開き、県の構想に基本的に合意するという文言を採択している。
国と県との駆け引きはさらに続く。
9月8日、県は4億7千万円もの費用をかけて、「米軍基地の整理・縮小と日米地位協定の見直しの賛否を問う」県民投票を実施する。本土のマスコミまで巻き込んだ大宣伝にもかかわらず、基地縮小に賛成した県民さえ約53パーセント弱という結果がでてしまった。「基地全面撤去は県民の総意」とうそぶいていた沖縄県庁は驚愕してしまった。
9月10日、大田知事は東京へと飛び、橋本総理にあっさりと「公告・縦覧代行応諾」の言質を与えてしまう。総理はこの時、基地縮小に努力すると表明し、直後に沖縄振興策のための特別調整費50億円と、沖縄県知事と関係閣僚で構成する沖縄施策協議会の設立を臨時閣議で決定。そして橋本総理は、沖縄県の国際都市構想実現に最大限の支援をすると表明した。まさにこの瞬間、国際都市構想は、沖縄県にとって「錦の御旗」となったのである。
あとは一気呵成。9月13日、大田知事は代理署名を正式に表明、14日と15日には「沖縄基地懇談会」が沖縄を視察し、17日には総理が来県して「沖縄の負担に反省とお詫びをする」とスピーチ、そして19日には衆議院の解散総選挙を正式に表明することになる。ちなみに、最終回の沖縄国際都市懇話会が9月26日に東京で開かれ、10月4日には第一回沖縄施政協議会が官邸で開かれている。
国と県の見事な談合ぶりと拍手の一つも送りたいところだが、実は沖縄県内では、国際都市構想は未だ認知されていないのである。
まず、このプロジェクトの地権者となる県軍用地等地主連合会は、当初から国際都市談話会への参加を拒否していた。昨年8月には、「基地縮小」を唱えていた全駐留軍用労働組合沖縄支部が分裂し、「基地縮小反対」を明言する全沖縄駐留軍労働組合が発足している。それだけではない。この構想は11月11日、一度として県議会にかけられることもなく、県庁三役があたかも県民の総意であるかのように装って決定しているのだ。
このような動きに対して、県民の反発は密かに、しかし着実に広がっている。11月17日に行われた那覇市長選で、大田県政の担い手ともいわれる親泊康晴氏(国際都市形成等市町村連絡協議会会長)が四選を果たす。ところが、その投票率は、自民党系の市議でさえ親泊氏に政策協調を申し入れたにもかかわらず、25.97パーセントという史上最低の数字であった。さらに沖縄本島北部市町村では、まるで県庁に反発するかのように、県都市部に展開する普天間基地などの米軍基地を積極的に誘致し、それによって実効的な地域活性化を計ろうとする動きがある。
ここで危惧すべきは、いまの沖縄県に国際都市構想を実現するだけの「力量」があるかということである。ひとつのエピソードを紹介しよう。
平成6年10月、沖縄県庁は日中友好のためとして、福建省福州市に同州と協力して地上12階地下2階建ての共同ビル建設に着手した。当初県側は、総工費3億5000万円のうち2億円を負担し、「追加出費はない」と県議会で答弁していた。ところが工事は大幅に遅れ、昨年3月、中国側から追加出費8500万円の請求と工事中断を通達されたのである。
県はこともあろうに、何の積載資料も示されていないのにもかかわらず、中国側に追加出費を約束し、12月の定例県議会に追認を求めた。ところがこの県議会で、中国との事業協定書には公印すら押されておらず、ビルの設計もすべて中国主導で進められていることが発覚してしまう。それどころか県庁側が議会の承認なしに建設費の一部を支出していたことまで明らかになった。
一枚岩と見られていた県政与党もさすがに憤慨し、県庁幹部による必死の根回しにもかかわらず、県議会では25対21で追加予算案を否決したのである。
国際都市の建設を云々する前に、いまの沖縄県に必要なのは、正常な「国際感覚」を学ぶことではないだろうか。
瀕死の沖縄経済
沖縄近代史において、県民が真剣に自立を目指して努力したのは昭和初期であった。昭和5年、県外で活躍していた県出身者が沖縄に集まり、沖縄振興促進期成会を結成して開発計画を策定。7年8月には沖縄県提出の沖縄振興15年計画として結実させ、同年12月には内務省案を踏まえて一部修正し、閣議決定に持ち込んでいる。
学校教育においても、県立第二中学校(現在の那覇高校)校長の志喜屋孝信氏(故人)らが先頭に立ち、「沖縄を他府県なみの教育水準に引き上げるには、秀才教育をもって当たるしかない」と本格的な人材育成に乗り出した。
同じく7年には、県民の浄財によって那覇市に移民会館が作られ、青年たちはここで合宿して徹底した事前教育を施された。当時の沖縄では、年平均4000人前後の青年が海外に移住していたものの、教育程度が低いために現地日本人会とトラブルを起こすケースが多かったからである。
当時の沖縄県民には猛烈な危機意識があった。昭和2年に発生した金融恐慌による不況で深刻な就職難に見舞われているというのに、京阪神地区で働く県出身者の勤務態度がすこぶる不評であり、これに独特な県民性が相まって、沖縄県民は本土社会で孤立しつつあるという危機感である。ところが現在、沖縄経済もまた不安定極まりないというのに、県民には危機感がまったく感じられない。
沖縄の県内人口は復帰時に比べて33.4パーセント増え、失業率は同じ期間の比較で4.2パーセント増大して7.2パーセント(本土は3.3パーセント=平成8年9月現在)。しかも失業者の過半が若者であることが深刻さを増している。ところが大田知事は、県内若年層の失業対策を国に頼って総理に直訴し、政府もまた平成9年度労働省予算の中に「沖縄若年層雇用開発推進事業費」を1億円計上した。同じ沖縄県民でも、戦前と戦後ではかくも意識に差があるのだ。
戦後沖縄県民の「甘えの構造」を、県内唯一のパソコンメーカーを経営する韓国出身の金泰源氏がこう批判している。
「沖縄には技術をもった企業が少なく、基盤がない。もし新しい企業が出てきても、経済界は公共事業や既得権益で食べており、出る杭はすぐに打ち潰される。補助をするところは補助しないといけないが、しがらみを打ち破ることも必要。保護と利権のぬるま湯に漬かっていては前には進まないことを県民自身が自覚する必要がある。(中略)
とかく沖縄では経済不振が外的な要因に結び付けられがちだが、県や経済界が経済活性化に真剣に取り組んでいるか疑問がある。(中略)予算を獲得してものを作ったらそれで終わりというのがこれまでのやり方。産業を育てるなら、インフラ整備を進めると共に人材育成に長期計画で取り組むべきだ」(「琉球新報」・平成8年9月23日付朝刊より)
県出身のロングアイランド大学教授、比嘉良治氏もこう述べている。
「沖縄経済は戦後だけでも軍事基地依存と国家財政依存で半世紀が過ぎた。このダメージを再生するには長期にわたる人間再生期間が必要だ。アメリカ人と日本人とでは確かにモラルの違いはあるが、社会保障制度に悩むアメリカの実態調査によると、生活保護を受けている家庭は代々保護を続けている可能性が強い。再生の可能性はというと、指導者2人でも長期間を要するとされている。
沖縄の経済自立にも基地返還後の短期計画と、二世代、三世代あるいはもっと長期の再生計画の二本立てが必要ではないだろうか。(中略)資源、財源に乏しい沖縄は人材育成に投資すべきで、(海外研修への)派遣の数はせめて人口の1%に達するように努力してもらいたい」(「琉球新報」・平成8年11月14日付朝刊より)
今年、沖縄は復帰25周年を迎える。昨年までに沖縄に投下された振興開発事業費の合計は4兆2943億円、これは今年実施される消費税値上げの増益分にほぼ匹敵する。それだけの資金を、人口比で約1パーセント、面積比でわずか0.6パーセントの沖縄に24年間にわたって注いだことになる。しかし、インフラは整備されたとはいえ、沖縄経済は自立するどころか、いまや瀕死の状況だ。
驚くべき実例をあげよう。
| (1). | 商業 県内不況の実勢を反映して、商業地価は5年続けて下落している。昨年の下落率5.7パーセントは、九州八県で最大。県内貸しビルの空室率は、県都那覇市のオフィスビルで12パーセントと、九州平均の3.0パーセントを大幅に上回る。しかも那覇市を除く市街地の閉業店舗率は35から45パーセント。県第二の都市である沖縄市の商店街では、187店舗のうち84店舗が廃業した。 |
| (2). | 観光 客数は年間目標の340万人を突破しているものの、客室単価のダンピングとのべ宿泊日数の短縮にともなって、県内主要10ホテルのうち経常利益を見込めるのは2社のみ。残りは三期連続の赤字決算になる見込み。 |
| (3). | 農業 復帰後、農業粗生産額は昭和60年の1160億円をピークに漸減し、平成7年現在で1008億円。とくに基幹作物であるサトウキビは、復帰後最低の収穫量を記録した。 |
減少ばかりが目立つ中で、基地関連の収入だけは着実に増加している。とくに米軍用地の賃借料は、復帰時に比べ4.7倍増の701億円。この間、軍用地面積が14.6パーセント減少したにもかかわらずである。
ついでに県内三行の上半期預金高を見てみよう。預金高合計2兆8450億円のうち、個人預金は前年比1.9パーセント増の1兆8078億円、法人預金は1パーセント増の7417億円となっているものの、実はいずれも軍用地借料などの特殊要因に依っている。皮肉にも、沖縄経済の基地依存度は相対的に高まる一方なのである。
おんぶにだっこの沖縄事情
沖縄に巣食う「甘えの構造」をこれ以上、放置するべきではない。そろそろ政府は、大田知事の「米軍基地の負担を全国民が引き受けるべきである」という文言に対し、「それでは基地削減に比例して、沖縄に対する基地関連補助費も削減する」と明言すべきではないか。それが結局は沖縄の自立を促することになるのだから。
しかし、昨年12月に決定された平成9年度予算大蔵原案を見ると、たとえ反基地運動を押え込もうという狙いがあったにしても、つかみ金をばらまいたという印象を拭えない。
目についたものを列挙する。
| ・ | 沖縄開発庁 沖縄関連の一括計上分が3332億円で、前年比の1.7パーセント増。このうち公共事業費(2918億円)の伸び率は1.9パーセントで、全国平均の1.3パーセントを上回る。 |
| ・ | 防衛庁 (1).基地周辺対策費・183億円(伸び率3.4パーセント。全国平均は2.7パーセント)(2).基地借地料・743億円(伸び率5.5パーセント)(3).基地交付金及び基地調整交付金・60億6300万円(上積み200万円。従来なら地価の下落にともなって削減される。沖縄だけ特別扱い) |
| ・ | 自治省 地方交付金に基地関連経費150億円をプラス。この半分の75億円が、沖縄県及び県内基地所在市町村に配分される予定。 |
| ・ | 総理府 「沖縄米軍基地所在市町村に関する懇談会」(沖縄基地懇談会)の提言に基づく基地所在市町村活性化特別事業の調査費16億8900万円(今後、数百億円から1千億円前後の事業が予定されている)。 |
| ・ | 各省庁 沖縄政策協議会で検討中の新たな沖縄振興策に対し、8年度補正予算で50億円を計上済み。 |
以上を合計すれば、沖縄関連予算はついに5000億円を突破。甘えの構造は解消されるどころか、より強固になったと見るべきだろう。さらに、この予算の編成期間になんとも不可解な動きがあった。
各都道府県知事は11月に入ると予算獲得のために各省庁を陳情にまわるのが常識だが、大田知事は上京もせず、16日から一週間、秘書随員7名をつれて東南アジア三カ国の視察旅行に出たのである。県は県で、東京の予算「対策本部」を「対策室」に格下げし、予算陳情活動を大幅に縮小。実はその裏で沖縄開発庁が奔走し、沖縄関連予算の編成作業に連日徹夜で取り組んでいたのである。
甘えも極まれりだが、橋本総理側近の動きも常軌を逸していた。
たとえば「沖縄基地懇談会」座長の島田晴雄慶大教授は、地方の行革及び競争理念の導入論者として知られている。当然、その言動が注目されたわけだが、島田教授は、沖縄を訪れるや「住民の目の高さで振興策を作る」との発言を繰り返し、相変わらずの「つかみ金ばらまき的施策」を提言する始末だった。
昨年十一月十二日に総理補佐官となった岡本行夫氏(外交評論家)の言動も、耳を疑いたくなるようなものばかりである。
「在日米軍基地の七八%が存在する沖縄はまさに一国二制度の様なものだから、沖縄県の主張する国際都市構想などの一国二制度を受け入れていいのではないだろうか」
(平成は八年十二月、県庁での発言より)
「東アジアの起点となるような施設群を持ってくる、それが私の夢だ。沖縄では新しい実験をしてみたらどうか、本土は沖縄に負のことだけを押し付けてきた。今度はプラスのこと、本土のどこでもやっていないことを沖縄でやっていい」(「琉球新報」・平成八年十一月十六日付朝刊より)
岡本氏は、沖縄基地懇談会と沖縄政策協議会の両委員を兼任している。沖縄県民が「夢」を語るのはともかく、しかるべき地位にある人物がその「夢物語」を助長するような発言をするのは、無責任の誹りを免れない。
沖縄への過大な予算投下に対して、地元では感謝するどころか、ほとんどが「当然」と受け止めている。当選まもない地元選出の自民党代議士でさえ「付くべきものが付いたままで」と言ってはばからない。
こういう姿勢を見るにつけ、「沖縄の自立」などやはり絵空事と断ぜるを得まい。
いま沖縄に必用なのは、何よりもまず競争原理の導入である。実は復帰の際、行政指導によって、本土同業種の沖縄進出は禁止された。その結果、県内企業は互いにもたれあって活気を失い、衰退の一途をたどっている。この傾向は言論界や学会にまで波及しており、社会の進歩そのものが停滞を余儀なくされている。
国は、いまこそ沖縄に、他府県で確たる活動をする様々は組織を進出させ、地元との競争や論争を促進するような積極的な政策に転ずるべきである。それによって、県民の複眼的な思考と自立心がはじめて醸成されるのではないだろうか。
それができないというなら、基地からの恩恵と国の財政補助というぬるま湯にどっぷり漬かった沖縄は、確実に「生活保護県」への道を歩むことになるだろう。